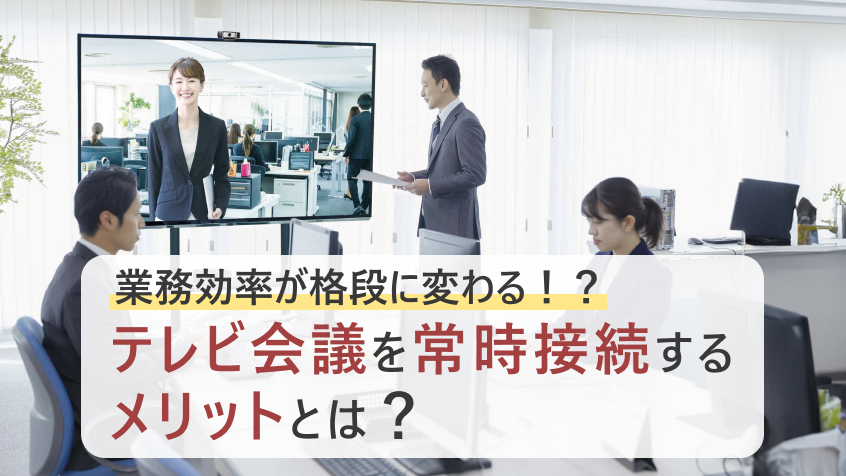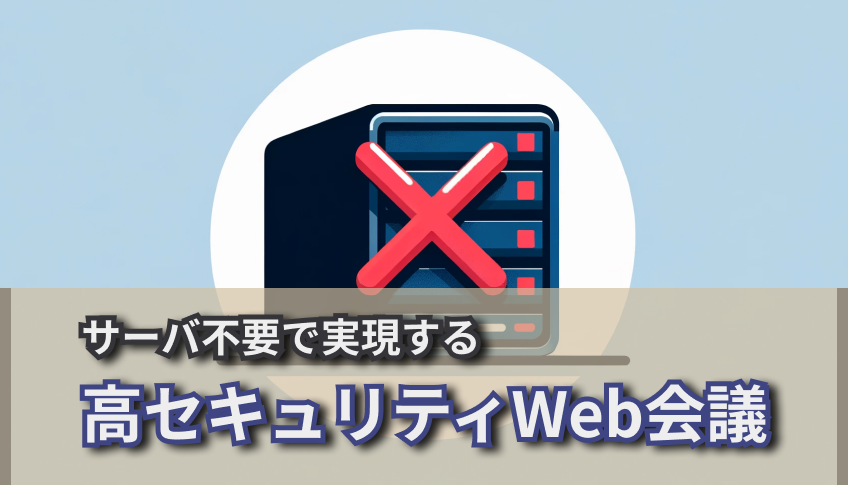オンライン接客システムは限られた人員の手数をサポートできる有効なツールですが、最近では一般的な店舗接客のほか、保険の相談や旅行代理店、役所の窓口など導入事例が広がっています。
そこで今回は、交番に導入された活用事例をご紹介します。
この事例は「空き交番」の対策にオンライン接客の仕組みが使われた事例です。
この記事の目次
警察官の不足による「空き交番」の問題
警察官の人材不足により、交番を閉鎖せざるを得ない状況が各地で発生しつつあると聞きます。
交番は、各地域住民の安心や安全を守るために設置されているもので、1つの施設の閉鎖は管轄地域の安心や安全を脅かすことにつながります。例えば緊急事態の発生時、相談先として身近な交番があれば、そこから安全を求めることができますが、施設自体が無くなると物理的に警察署へつながる手段が減ってしまいます。また「交番がある」という事実が抑止力になることも考えられます。閉鎖することで治安が悪くなる事態も予測されるでしょう。
-
「空き交番」:地域警察官の不在が常態化している交番。「空き交番」に該当しない交番であっても、事件・事故等に対応するため、配置されているすべての地域警察官が交番を一時的に不在にすることはあり得る。
交番が無人となる理由とは?
交番が無人になる主な理由の一つは、警察官が地域パトロールや緊急対応に従事していることです。交番勤務の警察官は、地域の安全を守るために巡回や事件・事故対応に出向く必要があり、その間は交番が一時的に無人となることがあります。また、交番の役割は「警察署」や「駐在所」と異なり、地域住民との身近な接点を提供することが主な使命ですが、人員配置の都合上、常に警察官が常駐するわけではありません。
さらに、人員不足も大きな要因です。全国的に警察官の人数が限られている中で、都市部では事件対応が優先され、地方では広範囲をカバーしなければならないため、交番が無人になりがちです。こうした状況が続くと、住民が「助けを求めたいときに誰もいない」という不安を抱えることにつながります。
しかし、これらの課題に対応するための対策として、交番では電話番号や案内掲示板の設置が進められています。加えて、最近では無人受付システムの導入も注目されています。このシステムでは、住民が設置されたタブレット端末や専用機器を通じて警察官と直接ビデオ通話を行うことができ、緊急時でも迅速に対応を受けられる仕組みです。また、簡単な手続きや情報提供がシステム内で自動的に処理されるため、住民の利便性が向上すると同時に警察官の負担軽減にもつながります。こうしたデジタル技術の活用は、交番が無人になる不安を解消する有効な手段として期待されています。
交番の無人化をビデオ通話で補う取り組み
このような問題に対し、交番の無人化をビデオ通話で補い、地域の安心や安全を維持しようという取り組みがなされています。交番に設置された機器を通じ、管轄の警察署と連絡が取れるようにするという空き交番への対策です。警察官が不在の時間帯でも、地域住民が安心して生活できるよう、防犯カメラや警報装置などの設置に加えて、さらにビデオ通話機能が導入されている場合があり、管轄の警察署と対話が可能になり、24時間体制での対応が可能となる仕組みがあります。
オンラインのビデオ通話 導入事例
ビデオ通話機能を導入している空き交番やそれに準ずる施設が、各地に増加しています。以下に、ビデオ通話機能を導入した無人交番の事例を紹介します。
警視庁「地域安全センター」の事例
東京都内にある警視庁管轄下の空き交番対策として、警察官不在時の来訪者が受話器を取ると自動的に管轄の警察署へつながるテレビ電話を設置しました。現在は、交番だったところが「地域安全センター」という名前に変わり、警官OBが勤務する施設と姿を変えているとのことでした。
特徴は、受話器を持ちあげると自動的に所轄の警察署につながるという点です。音声はハンズフリーでスピーカーからも出力され、緊急時に交番へ駆け込んだ人が慌てて動作をしても、接続先の警察官との通話が開始できるように設計されています。
交番へ勤務する警察官がパトロールに出たり、夜間不在になる場合にセットすることができ、人手の足りない時間帯を警察署で対応することで補うしくみになっているのです。
足立区「警察署直通テレビ電話」
足立区には「六町駅前安全安心ステーション ろくまる」という自治体が運営するユニークな交番があります。地元警察署と連携し、平日のみならず土日祝日も開所し、在籍する隊員の経歴が全員が元警察官とのこと。
1階の受付にボタンひとつで所轄の綾瀬警察署に直通するテレビ電話が設置されており、これは夜間の閉所時にも使用が可能となっています。自治体が運営する防犯施設と警察がテレビ電話で接続されるのは全国でも初めてなのだそうです。
六町駅前に安全安心ステーション
(”デジタル9ch”の(地上波)東京エリア局「TOKYO MX」Youtube公式チャンネルより)
受付システムと交番相談員の役割と活用方法
交番相談員は、地域住民と警察の橋渡し役を担う重要な存在です。近年、交番が一時的に無人となるケースが増える中、受付システムと交番相談員の役割が注目されています。交番相談員は、警察官ではないものの、地域住民からの相談や案内業務をサポートするために配置されており、犯罪の防止や地域の安全を守るために重要な役割を果たします。
受付システムと連携した交番相談員の役割
無人受付システムが導入されている交番では、住民がタブレット端末や専用機器を通じて、簡単な手続きや相談を行うことができます。しかし、技術だけでは解決できない複雑な問題も少なくありません。このような場合、交番相談員が住民の話を丁寧に聞き取り、適切な警察部署や担当者に引き継ぐことで、スムーズな対応が可能になります。
例えば、「落とし物の届け出」や「近隣トラブルの相談」など、日常的な問題については交番相談員が対応を行い、緊急を要する場合には警察官へ迅速に取り次ぎます。また、高齢者や外国人など、システムの操作に不慣れな人々に対しては、交番相談員がシステムの使い方を説明することで、住民が安心して利用できる環境を提供します。
受付システムと交番相談員の活用方法
無人受付システムと交番相談員が連携することで、次のような活用方法が可能です。
即時相談窓口としての利用
住民が無人受付システムを使用している際、相談内容によってはシステムだけで対応が完結する場合がありますが、複雑な案件や感情的な問題については交番相談員が対応することで、より細やかなサービスを提供できます。情報提供と防犯意識の向上
交番相談員は、住民に対して犯罪防止のためのアドバイスや地域の安全情報を提供する役割も担います。無人受付システムと連携して、住民に適切な情報を配信することも可能です。住民の利便性向上
交番相談員は、受付システムに加えて対面でも住民のニーズに対応するため、操作が難しい場合や個別に相談したい場合など、柔軟なサポートが可能です。
交番の未来を支える役割
無人受付システムと交番相談員は、警察官不在の交番において住民が安心して利用できる体制を構築する上で欠かせない要素です。この2つを組み合わせることで、効率的かつ効果的な地域安全の維持が可能になります。技術と人の力を融合したこの仕組みは、今後ますます重要性を増すでしょう。
簡単に使えるビデオ通話だから安心
オンライン接客のできる無料のオンラインツールは様々ありますが、「設置されたボタンを押す」「来訪を人感センサーがキャッチ」という簡単なステップで実運用が可能なオンラインツールは、多少の冷静さを欠いた状態の方でも接続が簡単です。急いで相談をしたい時に、この方式は非常に有用で、選ばれる大きな理由の1つとなっています。
無料のトライアルも受け付けています。お気軽にお問い合せください。
関連ページ
-
 リモート窓口・遠隔接客
リモート窓口・遠隔接客
“誰でも使える”リモート相談窓口とは?簡単操作で高齢者にもやさしいリモート対応を実現するには
自治体でリモート相談窓口システムを導入する際、最も重視すべき点のひとつは「住民が迷わず使えるかどうか […] -
 リモート窓口・遠隔接客
リモート窓口・遠隔接客
リモート相談窓口システムはLGWANで使えるか?自治体の三層分離に対応するシステムの考え方
自治体がリモート相談窓口システムの導入を検討する際、「LGWANで使えるのか?」「三層分離の構成に合 […] -
 リモート窓口・遠隔接客
リモート窓口・遠隔接客
自治体で導入する前に見極めたい──リモート相談窓口システムは“現場に合うか”実証実験で判断する
住民サービスの多様化、職員の人員不足、出張所間の業務格差といった課題を抱える中、リモート相談窓口シス […] -
 リモート窓口・遠隔接客
リモート窓口・遠隔接客
リモート相談窓口システム活用ガイド─リアルと同じように“顔を見て話せる”相談体験とは?
対面での相談を基本としてきた自治体の窓口業務に、リモートという新たな選択肢が加わってきました。 これ […] -
 リモート窓口・遠隔接客
リモート窓口・遠隔接客
リモート窓口の導入で顧客満足度アップ!具体的な効果と事例紹介
リモート窓口は、オンライン化が進む現代において、顧客満足度を向上させるための重要なツールとなっていま […] -
 リモート窓口・遠隔接客
リモート窓口・遠隔接客
【2025年版】 遠隔接客サービスの選び方とおすすめのシステム徹底ガイド
遠隔接客サービスは、ビジネスの未来を切り拓く重要なソリューションです。最新技術を活用し、接客業務の効 […]
インタビュー・導入事例
-
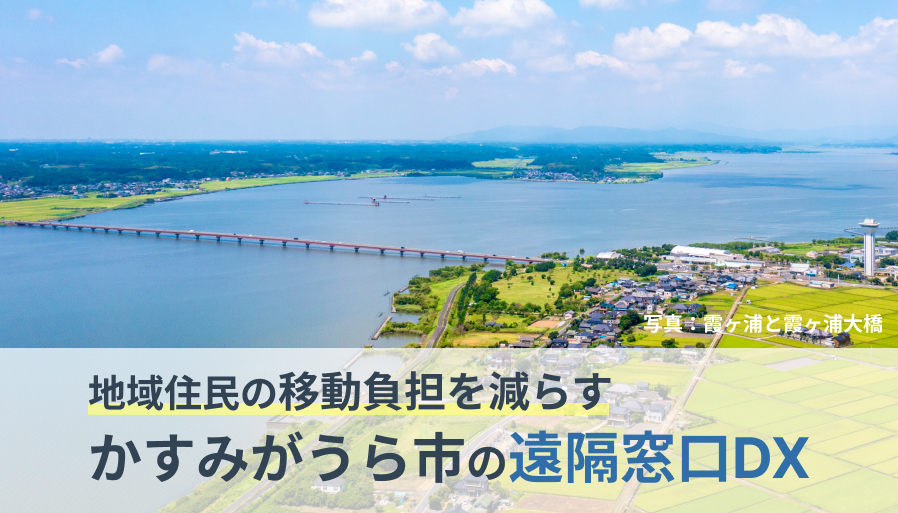
【テレ窓導入事例】地域住民の移動負担を減らす。かすみがうら市が実現した、庁舎の専門部署と出先機関をつなぐ遠隔窓口DX
茨城県かすみがうら市 様 Webサイト: https://www.city.kasumigaura. […] -

【テレ窓導入事例】角田市が進める、非来庁手続きを現場で支える運営のかたち― マイナンバーカード更新対応を支える、地域拠点との常時接続窓口
2020〜2021年度に実施されたマイナポイント第1弾で大量に発行された電子証明書が、有効期限を迎え […] -
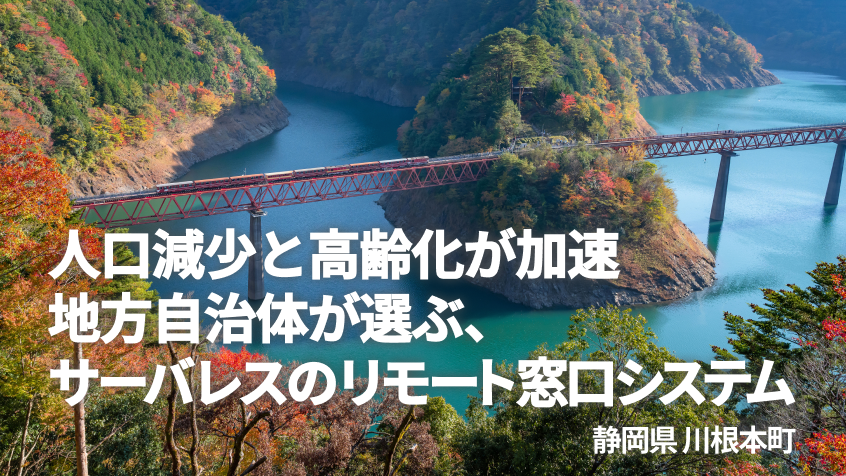
【テレ窓導入事例】高齢化率50%超(静岡県内2位)の川根本町からはじまる、高齢化・人口減少時代のサーバレス型リモート窓口DX
記事の要約 少子高齢化・人口減少に直面する自治体が、サーバレス型リモート窓口で実現した持続可能な住民 […] -
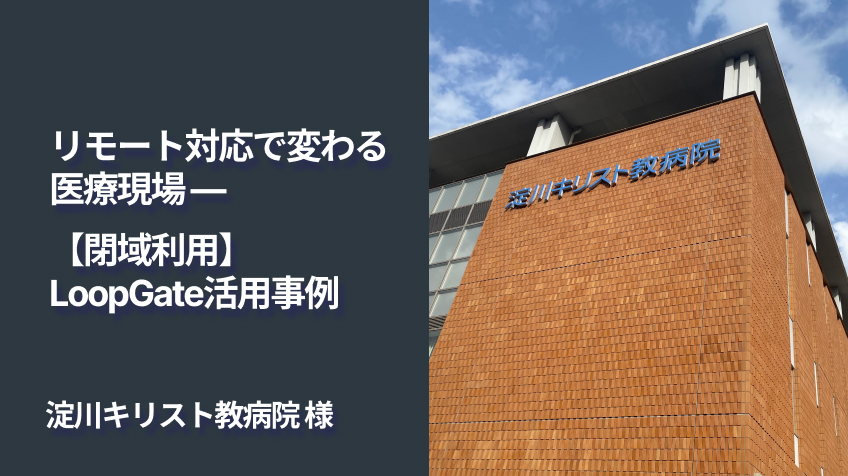
【LoopGate導入事例】閉域網環境での活用を進める、淀川キリスト教病院の非接触コミュニケーション運用― コロナ禍対応から平常時の活用にも発展
淀川キリスト教病院では、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、患者対応や院内連携における非接触でのコ […] -

【リモート窓口導入事例】合併後の庁舎二重化という課題にどう向き合うか――熊本県美里町が選んだ、住民が移動しなくても済む窓口のかたち
合併後の庁舎二重化や高齢化の進行は、多くの地方自治体が直面している課題です。熊本県美里町でも、住民の […] -

【お隣オフィス導入事例】店舗拡大でも「同じ空間で育てる」ーSILVER-BACKが実現した、スタッフ教育と日常フォローの常時接続運用
SILVER-BACKは、不動産売買事業や建築・リフォーム事業などを手掛ける不動産の専門家企業として […]