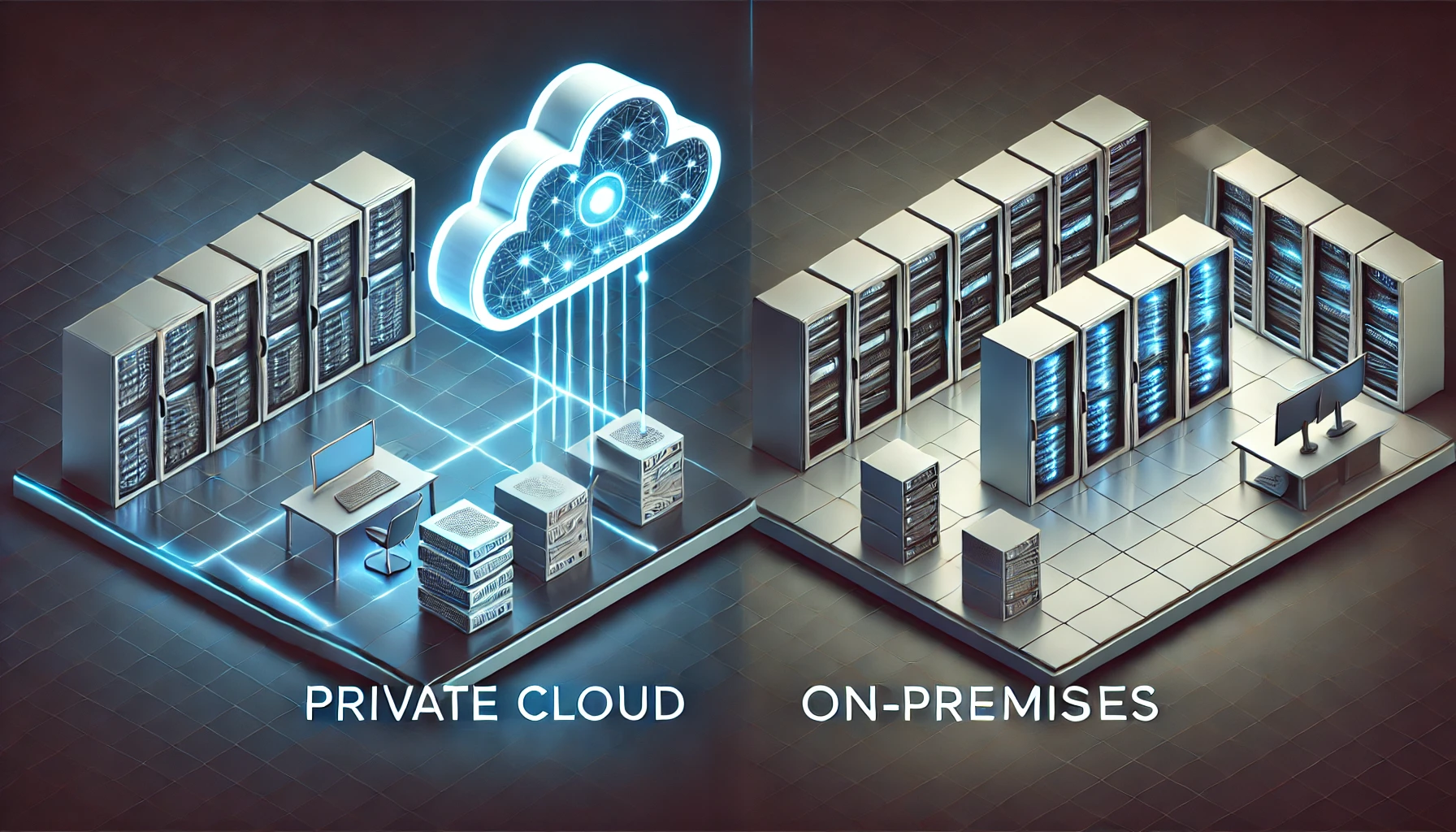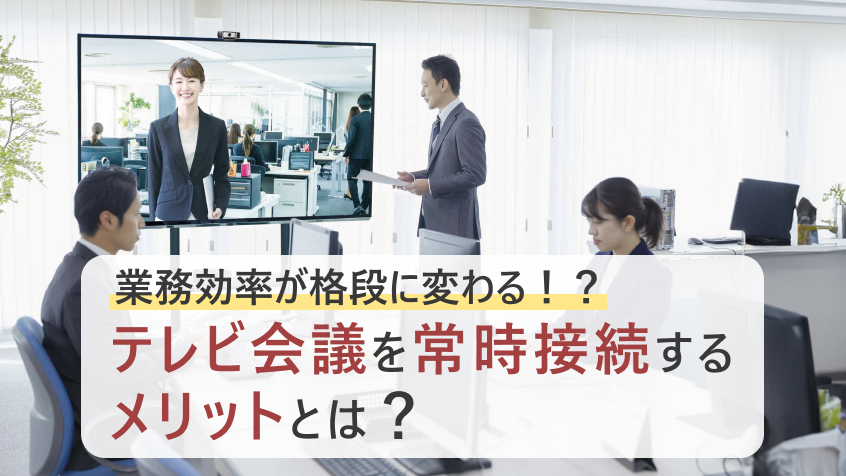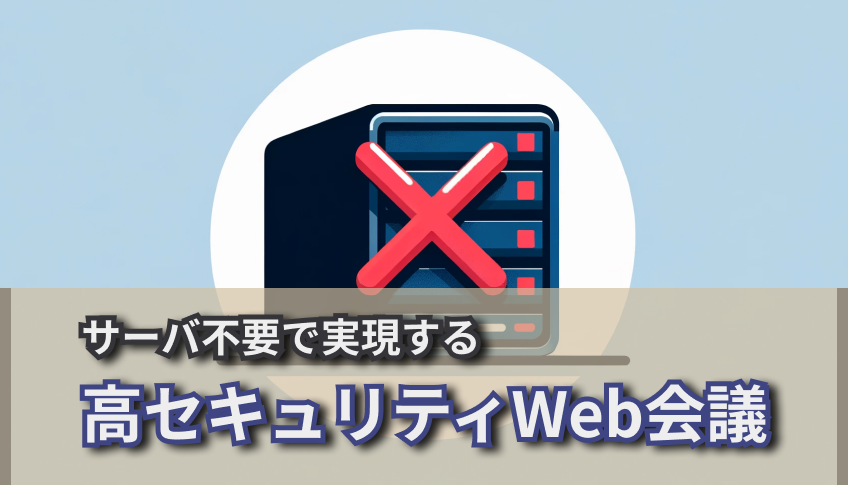企業がITインフラを選択する際、「プライベートクラウド」と「オンプレミス」の違いは、経営戦略に大きな影響を与えます。プライベートクラウドは柔軟性が高く、初期導入コストを抑えられる一方、オンプレミスはデータ管理やセキュリティ面での強みを持っています。
どちらを選ぶかによって運用コストや管理負担に違いが生まれるため、本記事では、プライベートクラウドとオンプレミスの違いを詳細に解説し、企業が最適な選択をするための判断基準を提示します。
この記事の目次
プライベートクラウドのタイプ
ホスティング型の特徴
ホスティング型パブリッククラウドは、AWSやMicrosoftなどのプロバイダーがインフラを管理し、企業が自社の専用区画として利用する型の例です。このモデルの大きな特徴は、オンプレミス環境と比較して初期投資を抑えつつ、スケーラビリティや柔軟性を確保できる点にあります。
企業は自社でサーバーを管理する必要がないため、ITリソースを効率良く活用できます。さらに、プロバイダーがインフラの管理を行うため、最新のテクノロジーやセキュリティ対策が施されることが多く、安心して利用できる環境が整っています。しかし、カスタマイズ性や特定のセキュリティ要件に関しては制限がある場合があり、選定には注意が必要です。ホスティング型は、特に迅速な導入やコスト効率が求められるプロジェクトに適しています。
オンプレミス型の特徴
オンプレミス型のシステムは、データセンターにおいて自社でサーバーやネットワーク機器を管理・運用するプライベートクラウド型の一例です。このモデルの最大の特徴は、企業がハードウェアを直接所有し、完全なコントロールを持つ点にあります。オンプレミス型は、パブリッククラウドと比較してカスタマイズ性とセキュリティの観点において優れています。企業は自身のニーズに合わせてシステムを細かく調整でき、機密データを自社内で厳格に管理することが可能です。
しかし、導入時には高額な初期投資が必要であり、設備の維持・管理にも専門的な知識と継続的なコストがかかります。また、技術の進化に伴い、定期的なアップグレードが求められるため、長期的な視野での計画が重要です。これにより、オンプレミス型は特に大企業や特定業種の企業において、セキュリティや柔軟性を重視する場合に選ばれることが多いです。
その他タイプとの違い:パブリッククラウドとは?
パブリッククラウドとは、インターネットを通じて提供されるクラウドサービスの一形態であり、複数の企業や個人が同一のクラウド基盤を共有して利用する仕組みです。代表的なサービスとしては、Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureなどがあります。
プライベートクラウドとの主な違いは、リソースの専有性と管理の自由度です。プライベートクラウドは、特定の企業専用に構築されるため、データの機密性やカスタマイズ性が高くなります。一方、パブリッククラウドは、共有リソースを利用するため、初期導入コストや運用負担が軽減される点がメリットです。
また、コスト面でも違いがあります。パブリッククラウドは従量課金制が一般的で、使用した分だけの支払いとなるため、スモールスタートが可能です。対してプライベートクラウドは、専用のハードウェアやデータセンターの構築が必要となり、初期投資が高額になりやすい特徴があります。
運用管理の観点では、パブリッククラウドはクラウドプロバイダー側で運用保守が行われるのに対し、プライベートクラウドは自社での運用管理が求められます。
これらの違いを理解した上で、セキュリティ重視の企業にはプライベートクラウド、コスト削減や柔軟性を重視する場合にはパブリッククラウドが適していると言えます。
企業のIT戦略において、プライベートクラウドとオンプレミスのどちらを選ぶかは、非常に重要な決断です。各アプローチには特有の利点と課題が存在します。プライベートクラウドは、パブリッククラウドとは異なり、専用のリソースを利用するため、高度なセキュリティとカスタマイズ性を実現できます。これはホスティング型のデータセンターで提供されることが多く、柔軟な型の例として挙げられます。
一方で、オンプレミスは自社内に物理的なサーバーを設置し、管理することで、データの完全なコントロールと所有権を確保します。選択にあたっては、企業のビジネスニーズ、予算、そしてITリソース管理能力を考慮することが不可欠です。例えば、プロジェクトにおいてスケーラビリティが求められる場合や、迅速な導入が必要な場合には、プライベートクラウドが適しています。
対照的に、既存のインフラを活用したい状況や、データを完全に制御したい場合には、オンプレミスが有利です。最適な選択を行うためには、各オプションのメリットとデメリットをしっかりと比較し、具体的なビジネス要件に基づいて決定することが求められます。
オンプレミスの基本知識
オンプレミスは、企業が自社内にサーバーやデータセンターを設置し、システムやアプリケーションを運用する型を指します。この形態は、パブリッククラウドやプライベートクラウドとは異なり、全ての管理を自社で行うことができるため、特にデータセキュリティやコンプライアンスの厳しい業界で重宝されます。
例えば、金融業界や医療分野では、オンプレミスの導入が推奨されることがあります。オンプレミスの利点としては、システムの全体を自社で管理できるため、セキュリティが高く、さらにカスタマイズ性に優れ、インターネット接続に依存しないためオフライン環境でもシステムを利用できることが挙げられます。
しかし、初期導入にはコストがかかり、運用には専門知識が必要となるため、中小企業には負担となることもあります。それでも、企業の特性やニーズに応じてオンプレミスが最適な選択肢となることは多く、導入時には目的や長期的な視野での運用を考慮することが重要です。
プライベートクラウドとオンプレミスを比較する
導入時のコストと期間
パブリッククラウドやプライベートクラウド、オンプレミスの導入にあたっては、それぞれ異なるコストと期間がかかります。例えば、AWSのようなパブリッククラウドサービスを活用する場合、初期投資が比較的抑えられ、短期間での導入が可能です。これは、クラウドプロバイダがインフラを管理しているため、導入企業はすぐにサービスを利用開始できるからです。特に、NW型のプライベートクラウドは既存のネットワークを活用する形で、スムーズに移行可能で、迅速な導入が期待できます。
一方、オンプレミスの場合、サーバーやネットワーク機器を自社で購入・設置しなければならず、初期コストが高く、導入に時間を要することが一般的です。したがって、企業は自社のIT環境やビジネスニーズを考慮し、どの選択肢が最適かを慎重に検討する必要があります。予算や導入期間に制約がある場合、パブリッククラウドやプライベートクラウドが優位性を持つことが多いです。
運用におけるコスト面の比較
パブリッククラウドの一例として、AWSを活用したホスティング型の運用は、コスト面での利点が多くあります。特に、運用費用の予測がしやすいことが挙げられます。従量課金制を採用しているため、使用量に応じた柔軟な費用管理が可能であり、急なコストの変動を抑えることができます。これに対して、オンプレミスの運用は、NW型の管理を自社で行う必要があり、ハードウェアの更新や保守、ITスタッフの維持費用が発生します。これらのコストは変動する可能性が高く、長期的には予算を圧迫する要因となり得ます。ただし、オンプレミスは初期投資が大きくなる傾向があるものの、ある規模以上ではランニングコストが削減されるケースも存在します。企業のニーズに応じて、どの運用方法が最適かを慎重に検討することが求められます。パブリッククラウドのガイドラインを参考にしながら、最適なコスト管理戦略を立案することが重要です。
カスタマイズ性と柔軟性
パブリッククラウドやオンプレミス型の「カスタマイズ性と柔軟性」は、現代の事業戦略において非常に重要です。例えば、AWSやMicrosoftを利用したパブリッククラウドでは、ユーザーが豊富なツールやAPIを活用してシステムを柔軟に構築することが可能です。これにより、ビジネスのニーズに応じた迅速なカスタマイズが実現します。
一方、オンプレミス型は自社管理のため、ハードウェアからソフトウェアまでを細部にわたって自由にカスタマイズすることができます。このため、特定の業務要件やセキュリティ基準に応じた独自のシステムを構築することが可能です。さらに、ホスティングの観点から見ると、クラウド環境ではリソースの増減が容易で、ビジネスの変化に迅速に適応できます。
オンプレミスでは、既存インフラを自社のペースで拡張・縮小することができ、長期的視点での柔軟な運用が期待されます。こうした特徴を理解し、企業の特性とニーズに最も適した選択をすることが事業成功の鍵となります。
スケーラビリティの観点での違い
パブリッククラウドとプライベートクラウド、およびオンプレミス環境のスケーラビリティには、顕著な違いがあります。例えば、AWSのような1型のパブリッククラウドは、グローバルなインフラストラクチャを活用し、迅速にリソースを拡張する能力を持っています。これにより、需要の変動に対して即座に対応可能であり、追加のハードウェアやサーバーを調達する必要がありません。
一方、プライベートクラウドは専用のインフラを使用するため、セキュリティやカスタマイズ性に優れつつも、パブリッククラウドほどの迅速さは欠けることがあります。しかし、ビジネスの特性に応じた柔軟なスケールアップやスケールダウンが可能です。これに対して、ホスティングサービスを利用したオンプレミス環境では、物理的なサーバーやストレージの追加が必要であり、リソースの拡張には時間とコストがかかることが一般的です。
このため、急激な需要の増加に対応するには、事前の計画と投資が不可欠です。さらに、オンプレミスでは、予測を誤ると過剰な投資やリソース不足に陥るリスクもあります。結果として、スケーラビリティを重視する企業にとって、パブリッククラウドやプライベートクラウドは状況に応じて理想的な選択肢となり得ます。
セキュリティとパフォーマンスの比較
パブリッククラウド型とプライベートクラウド型のホスティングを選択する際、セキュリティとパフォーマンスのバランスを慎重に考えることが求められます。例えば、プライベートクラウドはプロバイダーが最新のセキュリティ対策を講じており、セキュリティ面の安心感があります。さらに、クラウドベースのインフラストラクチャはトラフィックの変動に柔軟に対応し、高いパフォーマンスを発揮します。一方で、オンプレミスのデータセンターは、企業内部でのセキュリティ管理が可能で、データが外部に出るリスクを避けられるのが特徴です。パフォーマンス面でも、ネットワーク遅延を最小限に抑えることができるため、リアルタイム性が求められる業務に適しています。これらの選択肢を比べることで、組織のニーズに最も合ったホスティング型を選ぶことが重要となります。

メリットとデメリットを考える
ホスティング型プライベートクラウドの利点と課題
ホスティング型プライベートクラウドは、企業が自社のITインフラをクラウドプロバイダーに託し、柔軟にリソースを活用できるオンラインソリューションです。このモデルの利点としては、初期導入コストの削減やスケーラビリティの向上が挙げられます。
AWSなどの例に見られるように、必要な時に必要なだけリソースを追加できるため、ビジネスの成長に応じた柔軟な対応が可能です。また、クラウドプロバイダーによるインフラ管理により、企業は自社のコアビジネスに集中することができます。さらに、最新のセキュリティ技術の適用により、セキュリティ面でも安心です。しかし、課題としては、カスタマイズ性に制限があることや、データの所在に関する規制への対応が必要な場合があることが挙げられます。
また、ネットワークの帯域幅やパフォーマンスがプロバイダーに依存するため、サービスの品質が一貫しない可能性もあります。これらの利点と課題を理解し、ホスティング型プライベートクラウドが自社にとって最適かどうかを慎重に検討することが重要です。パブリッククラウドとプライベートクラウドの違いを理解し、自社にとって最適なクラウド戦略を選択することが求められます。
オンプレミス型プライベートクラウドの利点と課題
オンプレミス型プライベートクラウドは、企業が自社内で独自に設置し運用するクラウド環境を意味します。この型のプライベートクラウドは、組織がクラウド環境を完全に制御できるため、非常に高いカスタマイズ性を提供します。特に、業界固有の規制やセキュリティ要件が厳しい企業にとっては、このモデルが理想的な選択肢となります。データが外部のパブリッククラウドサービス(例:AWSなど)に出るリスクがないため、情報漏洩の可能性を最小限に抑えることが可能です。
しかしながら、オンプレミス型プライベートクラウドにはいくつかの課題も存在します。最初に挙げられるのは、導入時にかかる初期費用の高さです。加えて、ハードウェアやソフトウェアのメンテナンスにかかる運用コストも大きな負担となり得ます。このため、中小企業にとっては経済的な負担が重くなる可能性があります。さらに、スケーラビリティにも制限があり、急なリソース需要に対して柔軟に対応することが難しい場合もあります。しかし、これらの課題を解決すれば、オンプレミス型プライベートクラウドは非常に強力なIT基盤となるでしょう。
オンプレミスの利点と課題
オンプレミス型のシステムは、企業が自社内にサーバーを設置し、データセンターを活用することで、データ管理や運用を完全にコントロールできることが最大の利点です。特にセキュリティやコンプライアンスが重視される業種では、パブリッククラウドやプライベートクラウドにデータを預けるリスクを避けることができるため、オンプレミスは非常に有用です。また、カスタマイズ性が高く、企業のニーズに応じてハードウェアやソフトウェアの設定を自由に変更できるため、特定のビジネス要件に合ったシステム構築が可能となります。
しかし、初期導入費用が高額であることや、設備の維持管理に専門的な知識が必要とされることが課題です。さらに、スケーラビリティに関しても追加のハードウェア購入が必要となり、迅速なリソース拡張が難しい場合があります。これらの要素を考慮し、オンプレミス型を選択するかどうかを慎重に検討することが重要です。
用途に応じた選択肢
ホスティング型が適しているケース
ホスティング型プライベートクラウドは、特にリソースのスケーラビリティと迅速な導入が求められる企業に適しています。例えば、AWSのようなパブリッククラウドでは対応しきれない、特定のセキュリティ要件を持つ1型企業にとって、ホスティング型は理想的な選択肢となります。初期投資を抑えたい中小企業や、ITインフラの管理を外部に委託したい企業にとっても、ホスティング型の柔軟性は大きなメリットです。急速に変化する市場環境に対応するために、リソースの迅速な調整が必要なビジネスにおいても、ホスティング型の柔軟性は大いに役立ちます。
さらに、法規制によりデータの保管場所が厳しく指定されている業界でも、ホスティング型を利用することで、地域に根差したデータセンターを選択することが可能です。これにより、企業はコンプライアンスを維持しながら、安心して業務を遂行できます。ホスティング型を選ぶことで、企業はITリソースの運用負荷を軽減し、コアビジネスに集中することができます。
オンプレミス型が適しているケース
オンプレミス型が適しているケースでは、特定の条件や要件に応じてオンプレミス型のプライベートクラウドの導入が考えられます。以下にその具体的なケースをいくつか挙げます。まず、データの機密性が非常に高く、パブリッククラウドやAWS 1型などの外部サービスにデータを出すことがリスクとなる業界や企業においては、自社内にサーバーを設置することで、データの管理を完全に自分たちの手で行うことができます。金融機関や医療機関など、データの保護が最優先される場面では、オンプレミス型は理想的です。
次に、既存のITインフラやシステムとの高い互換性が求められる場合も、オンプレミス型の選択が適しています。特に長年にわたって運用されているレガシーシステムとの統合が必要な場合、カスタマイズ性と柔軟性を持つオンプレミス型は優れた選択肢です。
また、運用コストの長期的な削減を目指す企業にとっても、初期投資は大きくなるものの、クラウドサービスの利用料がかからないオンプレミス型は有利です。さらに、物理的なセキュリティを強化したい場合や、自社のセキュリティポリシーに基づいてインフラを設計したい場合にも、オンプレミス型が適しています。これらの要素を考慮し、自社のニーズに最も合った選択をすることが重要です。
オンプレミスが適しているケース
オンプレミス環境が適しているケースについて見ていきましょう。企業が独自のデータ管理を希望する場合、オンプレミスは非常に有効な選択肢です。特に、医療機関や金融機関など、高度なセキュリティが必要とされる業種では、自社内でデータを保持することで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。さらに、オンプレミスはカスタマイズ性に優れており、企業固有の業務プロセスに特化したシステムを構築できます。これにより、業務効率を最大化し、競争優位性を確保することが可能です。
また、長期的に安定した運用を望む場合、オンプレミスはコスト管理がしやすく、予算の見通しも立てやすいと言えます。システムのアップグレードやメンテナンスも自社で行うことで、外部に依存せず迅速に対応できます。これらの要素を総合的に考慮すると、オンプレミスは特定のニーズに対して堅実な選択肢となり得ます。
さらに、1型ホスティングやパブリッククラウド、プライベートクラウド、AWSなどのクラウドソリューションと比較しても、オンプレミスには独自のメリットがあります。例えば、データの完全なコントロールやカスタマイズの自由度などが挙げられます。
プライベートクラウドとオンプレミスの選択で失敗しないためのチェックポイント
プライベートクラウドとオンプレミスのどちらを選択するかは、企業のIT戦略を決める重要な決断です。ここでは、選択時に保存しておきたいチェックポイントを解説します。
1. 現状のITインフラと業務要件を分析
最初に行うべきは、自社の最新のITインフラと業務要件を詳細に分析することです。オンプレミスの場合、自社内にサーバーを構築するため、初期投資が大きくなる、高度なカスタマイズや物理的なセキュリティが求められる業界に適しています。一方、プライベートクラウドは、スケーラビリティや運用の効率化を重視する企業に向いています。自社が重視するポイントを明確にし、それに基づいて選択することが重要です。
2.導入コストと運用コストの比較
コストは、選択の際に最も重視される要素の一つです。オンプレミスでは、ハードウェアや運用管理のため人のリソースが必要であるため、初期費用が高くなる傾向があります。クラウドは初期費用を抑えつつ、月額のランニングコストが発生します。長期的な視点でのコストシミュレーションを行い、自社の予算に適した選択肢を見極めることが失敗を防ぐ鍵となります。
3. セキュリティ要件と規制への適合性
業界ごとに求められるセキュリティ基準や法規制への適合も、選択時の重要な要素です。例えば、金融業界や医療業界のように、データの保管やアクセス管理がセキュリティに求められる場合、オンプレミスの物理導入される場合には、データ認証やアクセス制御が独自の要件を満たしているか確認しましょう。
4.ベンダー投票のポイント
最後に、導入するベンダーの選定も成功のカギを握ります。提供されるサポートコンテンツや運用支援の存在、サービスの拡張性などを事前に確認することが重要です。また、無料トライアルやデモを活用するし、実際の運用感覚を考えることで、自社に最適な解決策を選ぶことができます。
以上のポイントを踏まえ、プライベートとオンプレミスの特徴を深く理解することで、自社の課題に適したITインフラを構築できるでしょう。 正しい準備を行うことで、選択の失敗を防ぐために、長期今後の成功は可能です。
プライベートクラウドとオンプレミスの将来展望
プライベートクラウドとオンプレミスは、それぞれ独自の強みを持ちながら、企業のデジタルインフラとして進化し続けています。今後のIT戦略を検討する上で、デジタルトランスフォーメーション(DX)への対応や主要ベンダーの動向を本セクションでは、DX時代における選択肢とクラウド・オンプレミスの未来を展望します。
デジタルトランスフォーメーション(DX)時代の選択肢
DX時代において、企業がデータを活用した競争力を高めるためには、柔軟性と拡張性を確保したITインフラが求められます。この中で、クラウドは、セキュリティとカスタマイズ性を重視する企業にとって特に、AIや機械学習を活用した分析ツールを統合することで、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
一方、オンプレミスは、特定の業務要件や法の規制に適合する柔軟性を持ち、DX推進の中でも重要な役割を果たします。例えば、金融や医療の分野では、物理的なデータ管理が必要とされるシーンが多く、オンプレミスはその価値を維持しています。
主要ベンダーが見据えるクラウドとオンプレミスの未来
主要なクラウドプロバイダーやITベンダーの戦略からは、クラウドオンプレミスが共存しながら進化していく未来が見えてきます。AWSやMicrosoft、Googleなどの大手プロバイダーは、ハイブリッドクラウドやエッジコンピューティングに注目し、オンプレミスとの暫定的な連携を実現するソリューションを提供しています。これにより、企業はデータのローカル管理とクラウド活用の両立を取り組むことができます。
一方、国内ではNTTやソフトバンクなど、国内法規制に対応したプライベートクラウドサービスを展開し、オンプレミスからの移行を支援する取り組みを進めています。 特に、災害対策やセキュリティに配慮したサービスが特徴で、日本企業のニーズに応えた独自の進化を実現しています。
今後、AIやIoTの普及に伴い、クラウドとオンプレミスの役割はさらに多様化すると予想されます。例えば、急速性が求められるエッジデバイスの普及により、オンプレミス環境が分散型インフラの一部として再評価されるる可能性があります。
業界別ユースケースで見る最適な選択肢
プライベートクラウドとオンプレミスの選択肢は、業界や業務内容によってその適性が異なります。ここでは、医療業界と小売業界を例に、それぞれの課題に応じた最適な選択肢を解説します。コスト管理のポイントを抑えることで、自社にとって理想的なITインフラを導入するヒントを提供します。
医療業界におけるセキュアなデータ管理
医療業界では、患者情報や診療記録機といった密性の高いデータを扱うため、セキュリティと規制遵守が最重要課題です。 特に、個人情報保護法や医療関連の法規制に適合したITインフラが求められます。
オンプレミスは、医療機関が物理的にサーバーを管理できるため、データ管理の透明性を確保できます。また、専用ネットワークを利用することで、外部からの不正アクセスを排除し、高度なセキュリティを実現し特に、地域医療連携が重要なケースでは、オンプレミスによるデータ保管が信頼される選択肢となります。
やがて、プライベートクラウドは、データのスケーラビリティと運用効率の向上を実現します。多層防御やデータ暗号化技術を備えたクラウドサービスは、セキュリティ要件を満たしながらも、運用負荷を軽減できるため、中小規模また、災害時のデータバックアップや遠隔診療のニーズが高まる中、クラウド型の柔軟性は魅力です。
小売業界のITコスト削減の工夫
小売業界では、ITインフラに求められる要件として、コスト削減と業務効率化が挙げられます。多店舗展開やオンライン販売を行う企業にとって、システムの導入と運用にかかるコストは経営に大きな影響を与えます。
プライベートクラウドは、初期費用を抑えつつ、拡張性の高いシステムを構築できるため、季節やキャンペーンによる急激な変動が激しい小売業界に適しています。また、クラウドを利用することで、店舗ごとに異なる在庫管理を行っていますシステムを統一し、データの一要素管理を実現します。 さらに、AIを活用した必要予測や顧客分析など、クラウド型ソリューションの高度な機能も利用可能です。
一方、オンプレミスは、安定したシステム運用を重視する場合に適しています。例えば、POSシステムや決済処理のように臨時性が求められる業務では、オンプレミスによる専用インフラが、障害リスクを考慮した根本的な選択肢また、サーバー運用を自社で行うことで、ランニングコストを長期的に抑えられるケースもあります。
ニーズに合ったソリューションを見つけよう
企業のITインフラの選択肢には、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス型ホスティングがあります。それぞれのソリューションは、異なる利点と課題を持ち、ビジネスのニーズに最適なものを選ぶことが重要です。パブリッククラウドはスケーラビリティに優れ、迅速なリソース調達が可能で、コスト効率の高さが魅力です。プライベートクラウドは、カスタマイズ性とセキュリティの高さが評価され、特にデータセンターでの利用に適しています。オンプレミス型は、完全なデータコントロールを提供し、特にセキュリティが重要視される業界での信頼性が高いです。
まずは、自社のビジネス目標とIT要件を明確にし、それに基づいて各ソリューションの特徴を一覧にまとめて比較しましょう。具体的な導入事例や業界のベストプラクティスを参照することで、最適な選択が可能になります。専門家のアドバイスを受けることで、より効果的なインフラ戦略を構築することができます。


関連ページ
-
 オンプレミス・閉域網での利用
オンプレミス・閉域網での利用
常時接続VPNのメリット・デメリットは?仕組みや導入の課題も解説
リモートワークの拡大により、セキュアな通信が求められる今、VPNを利用した常時接続が注目されています […] -
 オンプレミス・閉域網での利用
オンプレミス・閉域網での利用
社内LANで実現するテレビ会議の高品質化とそのメリットを徹底解説
社内LANを活用したテレビ会議は、インターネット回線に依存せず、安定した通信環境と高いセキュリティを […] -
 オンプレミス・閉域網での利用
オンプレミス・閉域網での利用
閉域網を活用したWEB会議のセキュリティ対策:最適かつ効率的なシステム構成を解説
閉域網対応のWeb会議システムWEB会議の普及が進む中、セキュリティリスクに対する対策はますます重要 […] -
 オンプレミス・閉域網での利用
オンプレミス・閉域網での利用
Web会議×専用回線で実現する“ローカル”な高品質接続術
「Web会議が不安定で困っていませんか?」社内会議や拠点間ミーティングでの音声の遅延、画面のフリーズ […] -
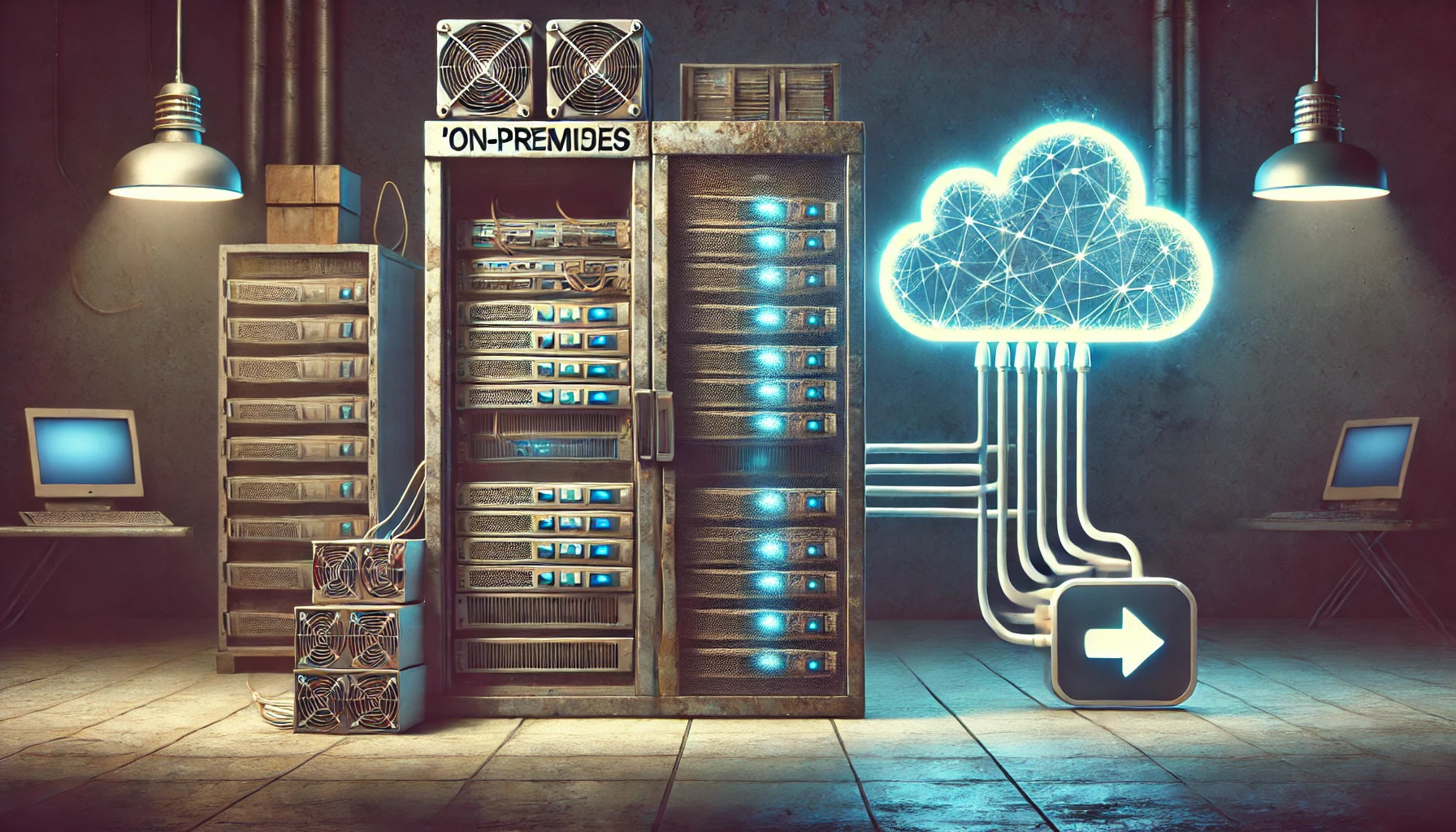 オンプレミス・閉域網での利用
オンプレミス・閉域網での利用
時代遅れと言われるオンプレミスの真実:まだ選ぶ理由とは
オンプレミスは時代遅れなのか? クラウドサービスの急速な普及に伴い、「もう時代遅れでは?」という声が […] -
 オンプレミス・閉域網での利用
オンプレミス・閉域網での利用
テレビ会議専用機とzoomなどの無料アプリを比較!選び方ポイントを紹介
オンラインコミュニケーションの普及に伴い、Google MeetやSkypeなどの無料Web会議アプ […]
インタビュー・導入事例
-
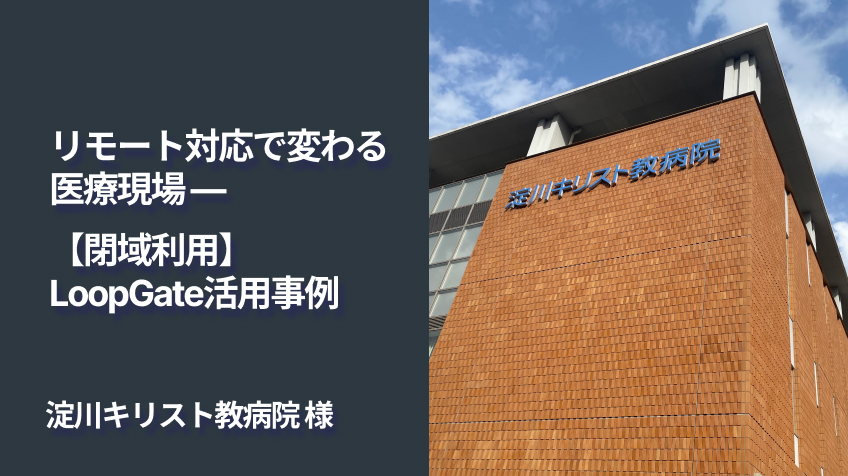
【LoopGate導入事例】閉域網環境での活用を進める、淀川キリスト教病院の非接触コミュニケーション運用― コロナ禍対応から平常時の活用にも発展
淀川キリスト教病院では、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、患者対応や院内連携における非接触でのコ […] -

【LoopGate導入事例】東日本銀行が常時接続で変えた拠点間連携「もう一人で悩まない!相談できる隣人が全社に」(銀行×ナレッジ共有)
本記事の要約 東日本銀行では、多店舗体制ゆえに起きやすい「店舗間の見えない壁」や、若手・新任者が抱え […] -

【LoopGate導入事例】愛媛県警察本部がオンプレミス環境で31拠点を接続。会議・研修から有事の迅速な連絡までを支えるテレビ会議基盤を構築。
本記事の要約 会議・研修の効率化と災害時の即応体制を同時に強化 愛媛県警察本部では、広域に点在する拠 […] -
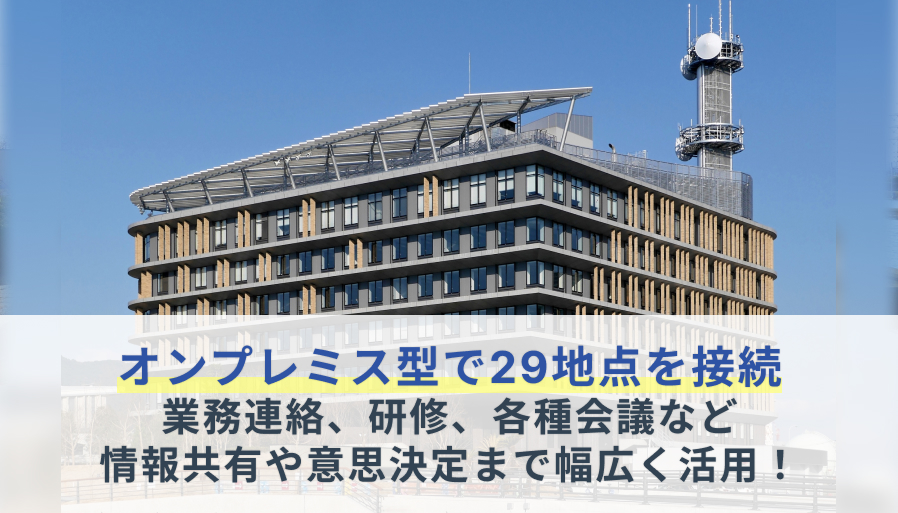
【LoopGate導入事例】オンプレミス型で29地点を接続。業務連絡、研修、各種会議などでの情報共有や意思決定まで幅広く活用!
業務の合理化、働き方の見直し、災害警備体制の強化など、職場環境の向上を目的として 長崎県は、東西21 […]