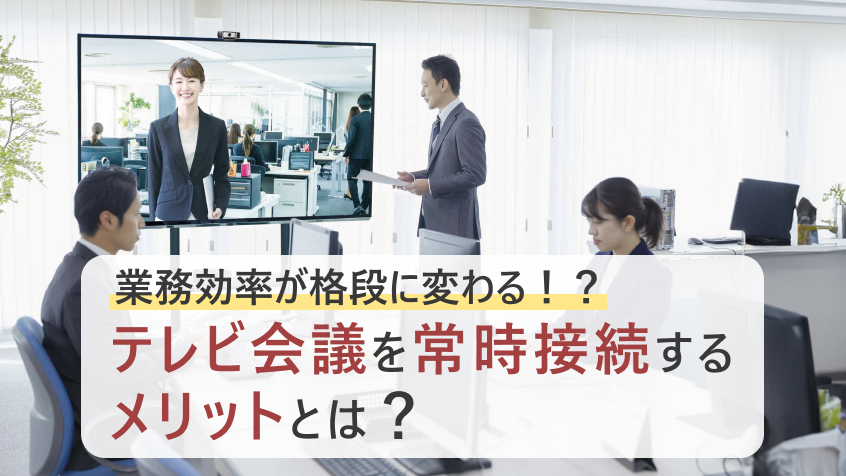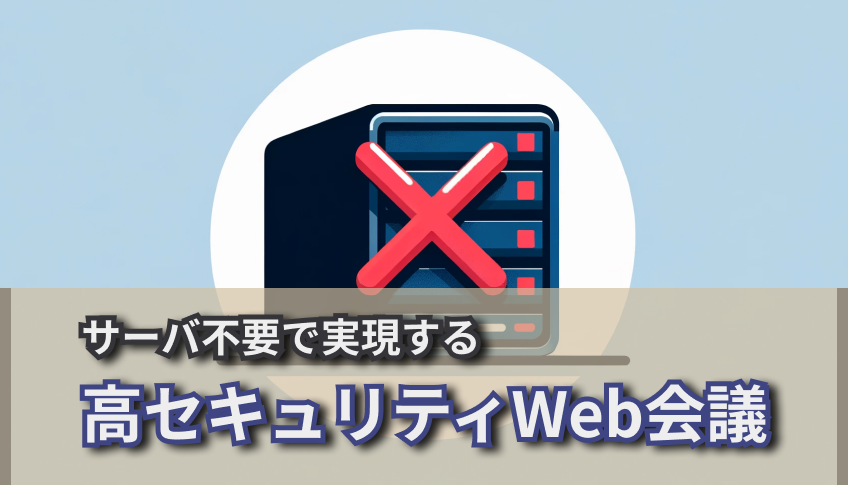対面での相談を基本としてきた自治体の窓口業務に、リモートという新たな選択肢が加わってきました。
- 来庁が困難な高齢者や遠方在住者への対応
- 多言語窓口の整備
- 限られた人員での業務継続など
これらの課題に応える手段として、「リモート相談窓口システム」による窓口のDX化の取り組みは多くの地方自治体で拡大しています。とはいえ、ただ映像通話ができる仕組みを入れれば良いという話ではありません。住民にとって“使いやすく”、職員にとって“運用しやすく”、かつネットワークやセキュリティなどの自治体固有の制約にも適応できる仕組みが求められます。
本記事では、自治体でリモート相談窓口システムの導入を検討する際に、押さえておきたい視点や比較のポイントを整理し、「どの製品が良いか」ではなく、「目的に対して、何を重視して選べばよいか」という観点から、導入成功のヒントを探っていきます。
この記事の目次
リモート相談窓口システムで必要な要素とは?
自治体の導入検討担当者の多くが感じる疑問や迷いとして、以下のような点をよくお聞きします
- 高齢者や機械に不慣れな方でも本当に使えるのか?
- 職員が他業務と兼務しながらでも対応できる仕組みか?
- LGWANや三相分離など自治体ネットワーク構成に対応しているか?
- 稟議や調達に耐えうるだけの根拠や定量的な効果が見えるか?
- 過疎地域や出張所・診療車など特殊な運用ケースにも対応可能か?
こうした疑問は、サービス紹介サイトや比較表だけでは解消できないものです。
そこでまずは、自治体向けに特化した「比較検討に必要な視点」で状況に合うかどうかを評価・整理することがとても大切です。
リモート相談窓口システム選定5つのポイント
- リモート相談窓口システム選定ポイント
-
- 操作性と定着のしやすさ
- LGWANや三相分離に対応できるネットワーク構成か
- PoC(実証実験)で現場に合うか検証できるか
- 人材配置の最適化につながる運用モデルか
- 活用領域や導入事例
1.操作性と定着のしやすさは、住民と職員の両方から見極める
住民サービスとしての相談窓口において、「誰でも迷わず使えること」は大前提です。ボタン一つでつながるシンプルなUI、タッチ操作、言語切り替え機能などは、高齢者対応において特に重要です。
一方、職員側も日常業務の一部として対応するため、ストレスなく着席・応対できる仕組みであることが求められます。操作負荷の少なさ、応対記録のしやすさ、回線管理の手軽さなどが比較の観点となります。
誰でも使えるUX設計の工夫について詳しくはこちらの記事もご覧ください
- 誰でも使えるUX設計の工夫
- “誰でも使える”リモート相談窓口とは?簡単操作で高齢者にもやさしいリモート対応を実現するには
2.LGWANや三相分離に対応できるネットワーク構成か
自治体においては、ネットワーク要件の制約が導入可否を大きく左右します。
- LGWAN(業務系アプリ利用ネットワーク)
- インターネット接続系(住民サービスや外部との通信)
- 住基ネット(住民基本台帳などの専用環境)
いわゆる「三相分離」と呼ばれるネットワーク分離環境に適合する構成が組めるかどうか。また、クラウド/オンプレ/閉域型など、調達ポリシーに応じた構成選択が可能かもポイントです。
LGWAN・三相分離の考え方について詳しくはこちらの記事もご覧ください
- LGWAN・三相分離の考え方
- リモート相談窓口システムはLGWANで使えるか?自治体の三層分離に対応するシステムの考え方
3.小規模なPoCで“現場に合うか”を検証できるか
いきなりの全庁導入ではなく、まずは特定の出張所・部門でのトライアル(PoC)を実施する流れが一般的です。
- 通信品質は問題ないか
- 職員の運用負担は増えないか
- 住民からの問い合わせは減ったか
- 導入前後で待機時間や案内数に差が出たか
これらを無償PoCで事前に実証できるかどうかは、導入判断を左右する重要な要素です。
実証実験(PoC)について詳しくはこちらの記事もご覧ください
- 実証実験(PoC)について
- 自治体で導入する前に見極めたい──リモート相談窓口システムは“現場に合うか”実証実験で判断する
4.人材配置の最適化につながる運用モデルか
自治体にとっての投資対効果は、「利益」ではなく“限られた人材の有効活用”です。
- 窓口に常駐しなくても、本庁から出張所の応対が可能
- 専門職員の“巡回”を減らし、窓口の平準化を図る
- 離島診療や移動市役所(お出かけ市役所)などでの拠点間連携
このような運用モデルが実現できれば、単なるコスト削減ではなく、持続可能な住民対応体制が構築できます。
5.活用領域が広がることで住民サービスの公平性が高まる
すでに一部の自治体や医療機関では、リモート相談窓口システムを活用して医療機関と連携した離島医療支援の体制構築やオンライン診療車の導入、来庁不要で窓口が赴く「お出かけ市役所」といった窓口業務を応用したの活用領域の拡大が活発です。
- 離島に住む住民が、本庁の担当職員と直接相談できる
- 医師が常駐できない地域でも、映像・資料を使った事前診察が可能
- 移動型行政サービス(車載窓口)との組み合わせによる展開
地域格差を解消するインフラとしても、リモート相談窓口システムは今後ますます活用される場面が増えていくと考えられます。
導入を成功させるには「自庁にとっての選定軸」を明確に
リモート相談窓口システムの選定においては、「どれが優れているか」ではなく、“自庁に合うか”を判断する視点が求められます。
- 現場の課題に合っているか?
- ネットワーク環境に適応できるか?
- 導入後の運用が職員にとって負担にならないか?
- 住民にとって“使いやすく、伝わりやすい”設計か?
それらを判断するうえで、比較・体験・対話のプロセスは不可欠です。選定に関わるすべての関係者が、同じ視点で評価できる材料を揃えることが成功の第一歩になります。
リモート相談窓口システムの選択肢に「テレ窓」
ここまでご紹介したリモート相談窓口システムの選定ポイントの中で、是非「テレ窓」をチェックしていただきたいと思います。
テレ窓は「簡単に操作できて、リモート相談窓口に特化した」システムになり、導入検証から実際の導入設置、テクニカルサポートのカバーを行えるサービスです。
まずは導入テストから、色々と試して検証していただければと思います。
リモート相談窓口を詳しく知りたい方へ
リモート相談窓口システム テレ窓
無料資料配布中!
リモート相談窓口システム
テレ窓
無料資料配布中!
多くの地方自治体で採用、LGWANにも対応したリモート相談窓口システム「テレ窓」
詳しい内容が掲載された資料を無料配布中です!
関連ページ
-
 リモート接客・無人受付
リモート接客・無人受付
“誰でも使える”リモート相談窓口とは?簡単操作で高齢者にもやさしいリモート対応を実現するには
自治体でリモート相談窓口システムを導入する際、最も重視すべき点のひとつは「住民が迷わず使えるかどうか […] -
 リモート接客・無人受付
リモート接客・無人受付
リモート相談窓口システムはLGWANで使えるか?自治体の三層分離に対応するシステムの考え方
自治体がリモート相談窓口システムの導入を検討する際、「LGWANで使えるのか?」「三層分離の構成に合 […] -
 リモート接客・無人受付
リモート接客・無人受付
自治体で導入する前に見極めたい──リモート相談窓口システムは“現場に合うか”実証実験で判断する
住民サービスの多様化、職員の人員不足、出張所間の業務格差といった課題を抱える中、リモート相談窓口シス […] -
 リモート接客・無人受付
リモート接客・無人受付
リモート相談窓口システム活用ガイド─リアルと同じように“顔を見て話せる”相談体験とは?
対面での相談を基本としてきた自治体の窓口業務に、リモートという新たな選択肢が加わってきました。 これ […] -
 リモート接客・無人受付
リモート接客・無人受付
リモート窓口の導入で顧客満足度アップ!具体的な効果と事例紹介
リモート窓口は、オンライン化が進む現代において、顧客満足度を向上させるための重要なツールとなっていま […] -
 リモート接客・無人受付
リモート接客・無人受付
無人店舗とは?導入の背景・メリット・事例・課題まで徹底解説
近年、注目される「無人店舗」は、小売業界の新潮流です。この無人化された仕組みは、テクノロジーを活用し […]
インタビュー・導入事例
-

【LoopGate導入事例】武蔵村山市:離れた庁舎を「テレビ窓口」で直結。遺族に寄り添う、移動不要の「おくやみワンストップ窓口」を実現
東京都武蔵村山市Webサイト: https://www.city.musashimurayama.l […] -
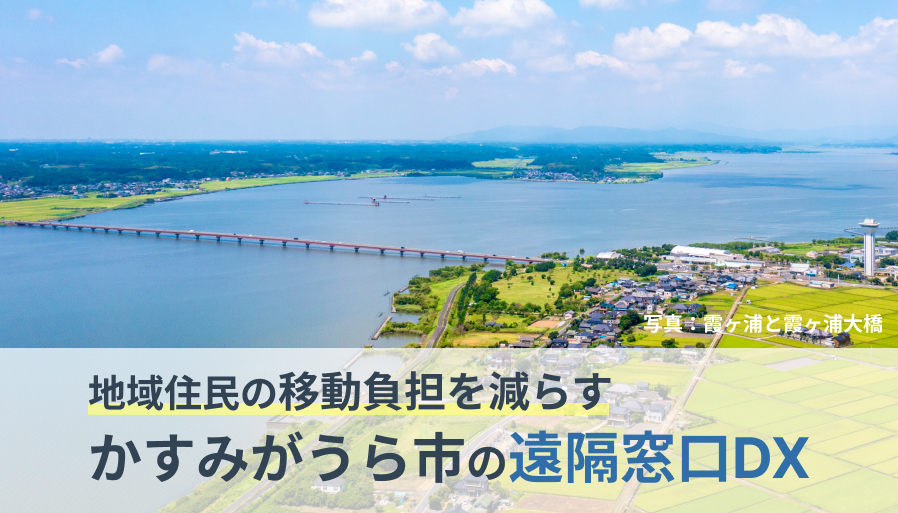
【テレ窓導入事例】地域住民の移動負担を減らす。かすみがうら市が実現した、庁舎の専門部署と出先機関をつなぐ遠隔窓口DX
茨城県かすみがうら市 様 Webサイト: https://www.city.kasumigaura. […] -

【テレ窓導入事例】角田市が進める、非来庁手続きを現場で支える運営のかたち― マイナンバーカード更新対応を支える、地域拠点との常時接続窓口
2020〜2021年度に実施されたマイナポイント第1弾で大量に発行された電子証明書が、有効期限を迎え […] -
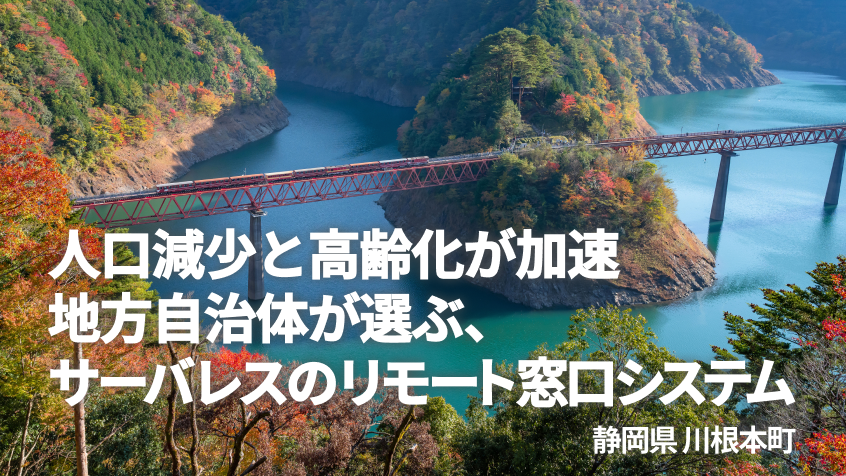
【テレ窓導入事例】高齢化率50%超(静岡県内2位)の川根本町からはじまる、高齢化・人口減少時代のサーバレス型リモート窓口DX
記事の要約 少子高齢化・人口減少に直面する自治体が、サーバレス型リモート窓口で実現した持続可能な住民 […] -
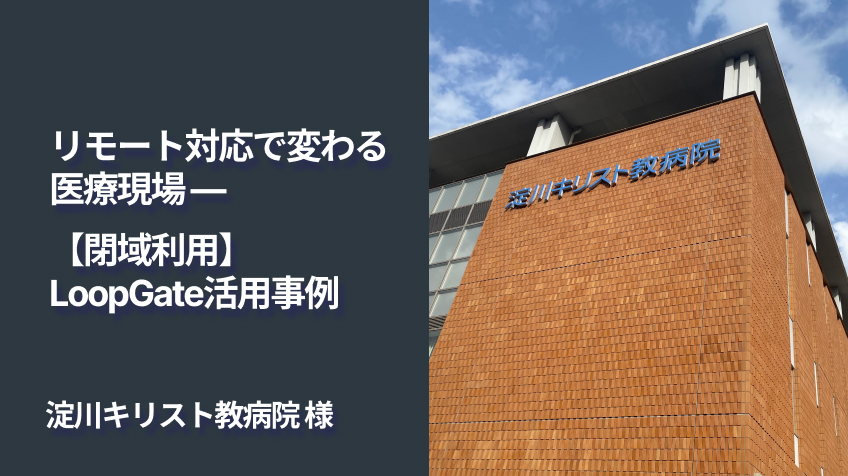
【LoopGate導入事例】閉域網環境での活用を進める、淀川キリスト教病院の非接触コミュニケーション運用― コロナ禍対応から平常時の活用にも発展
淀川キリスト教病院では、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、患者対応や院内連携における非接触でのコ […] -

【リモート窓口導入事例】合併後の庁舎二重化という課題にどう向き合うか――熊本県美里町が選んだ、住民が移動しなくても済む窓口のかたち
合併後の庁舎二重化や高齢化の進行は、多くの地方自治体が直面している課題です。熊本県美里町でも、住民の […]